
当初は石器とか手で脱穀
当時は、お米に麦やアワ、ヒエなどの雑穀類を混ぜ、おかゆのようにどろどろとやわらかくして食べていたとされている

竹や棒切れで稲を挟みしごいて脱穀
今から約3000年前の縄文時代後期(紀元前1500年頃)にはすでに大陸から稲作が伝わって来たと云われている?
その後、弥生時代前期(紀元前300年頃)には北九州から中国・四国・近畿地方へと水稲耕作が広がった。
現在のようなお米の食べ方になったのは平安時代になってからと云われている
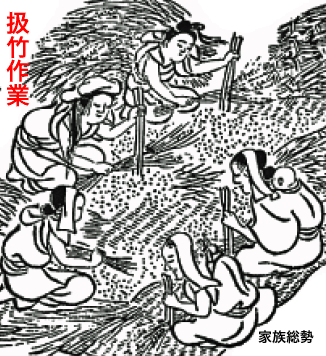
竹を縦に割り、少しの隙間を作り一端を縛る。その間に稲を入れて籾をしごき取る
 連枷(れんが)
連枷(れんが)「からさお」「めぐり棒」「くるり捧」などとも呼ばれ、竹の柄の先端に横木をわたし,この横木に回転できるようにした堅木〈または竹を編んだもの)を取り付け,むしろに敷き広げ,これを上からたたいて脱穀

二見式稲扱器(別名:金扱器カナゴキ)
歯の列が直線状の脱穀器
明治末期から大正にかけて使われたが、さらに能率のよい回転式の足踏脱穀機が普及し、千歯扱の時代が終わる

東野式千歯稲扱器
普通の直状歯杆ではなく、歯裂面の裏面中腹を約1cm凹ませて弓形としたのが特徴
(「扱く」の字の通り籾をもぎ取る)

2人扱用で,扱爪の形状は逆V字形,回転胴の両側部は勢輪を兼ねた大正末期〜昭和初期

戦時中の昭和20頃まで活躍
回転胴を足で駆動させ廻し脱穀
 (昭和25〜29年頃)
(昭和25〜29年頃)V字刃と押さえ刈り鎌の組み合わせ、人力で押して数株を刈るが無結束機
ノコギリ鎌からバインダーに至までの僅かな期間

戦後、まもなく登場した「刈り取り結束機」は作業の高能率なエンジン付農機具(昭和30年頃)
しかし、稲木掛けを必要とするのでコンバインの時代へと遷る
稲藁の保存保管は田に「つぼき」として乾燥させた後、納屋等に取り込み保管
または、堆肥を積んだり、カッターで短く切断して圃場に撒いたりする。

大正末期に国産の石油エンジンが開発された動力を使った脱穀機。脱穀中は手で持っていなければならない。下扱き式の脱穀機は昭和4年に開発

稲木掛けした束を運んできて脱穀
当初は人の手で「稲こき」をしていたが、戦後自動脱穀機が普及(エンジンには発動機や電気モーターからベルトで駆動)

自走式全自動脱穀機(ハーベスター)
稲木から稲束を搬入しなくても良くなくなる
エンジンを載せキャタビラが付き自走全自動脱穀機
農作業の省力化が進む写真拡大

ハーベスターの構造
稲藁切断機は付属していない
拡大写真

現在使用中のコンバイン
刈り取り・脱穀・藁切断を総て処理
拡大写真
(1975年頃より煙突のないコンバインで籾は袋に入れて運んでいたが、今は籾袋を持ち運ぶこともない)

稲木を作る必要もなくなり、刈り取りから脱穀までを処理し、稲藁はカッターで切断して圃場にばらまき作業能率の超アップ(1993年頃より)
(1975年頃より煙突のないコンバインで籾は袋に入れて運んでいたが、今は籾袋を持ち運ぶこともない)
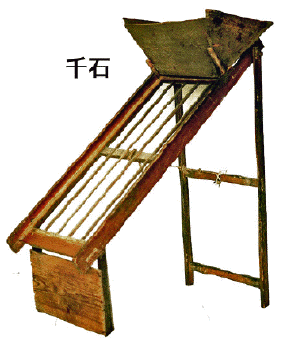
雑穀調整用機具・千石
江戸〜明治初期の選別器

明治時代に活躍した分離選別用万石
江戸時代から昭和10年代の土臼籾すり時代にかけて広く使われた

江戸から昭和時代にかけて活躍した籾と玄米の分離選別用機具。

昭和20年以降の戦後も活躍
縦線とも云われ、縦に張られた無数の線と線との間隔と傾斜角度を調整して選別。

種々改良された米選機 写真拡大
編み目の異なった金網を取り替えたり、米の流れる角度を変えて選別
現在でもこの網選別方式は、万石選別式動力籾すり機に生かし活躍

現代の籾摺り機「ネオライスマスター」
昔の籾摺りから玄米選別までの総てをマイコン内蔵で処理

現代使われている籾摺り機
編み目の異なる震い4〜6枚が振動して選別(本体の使用状況はこちらへ)

左記籾摺り機「ネオライスマスター」の玄米選別までの仕組み 拡大写真
拡大写真より、千石・万石・米選機の仕組みを引継ぎ、より効率よく改良されたことが分かる
乾燥後は籾摺り機で玄米になる
詳細は、「稲作収穫編3]へ